【テーマ】
全SAの節水は、琵琶湖水位0.44mmに匹敵!■全国の高速道路の サービスエリア・パーキングエリアで、「自動水栓の手洗い」を利用する人は、年間、推定で延べ約9億9千万人にも上りますので、その消費する水道水量も膨大です。
■この手洗い水の節水が、自動水栓の水量調節をすることで大幅に可能です。
・水道水の節水金額:7千7百万円/年
・節水量:30万トン/年(一般家庭990軒分)
・琵琶湖の水位に換算:1年間0.44mmにも相当
■各地の貯水ダムの渇水対策、省資源のひとつのヒントともなります。
SA・PAの手洗い自動水栓の節水面の問題・・・観察結果(発見した問題)…自動水栓について
サービスエリア・パーキングエリアの「手洗い自動水栓」の使用状況について、一部のSA・PAで観測し、「蛇口からの水流が強すぎる」 ことから、節水の観点で次の問題のあることが分かりました。
(問題の内容)
●手洗い後、蛇口から手を引いた後も、水は必要以上にしばらくは流れ続け、水が無駄に消費されている。
●元栓の調節が悪いことが原因です。(水量を適切に絞っていない)
(SA・PAの利用者数戸消費水量)
●全国で、年間、延べ約10億人もの多くの人がSA・PAの自動水栓手洗いを利用していると推定されますので、たとえ個々の水量が小さくても無駄水量が大きくなります。
●節水すると、全体での効果も大きくなります。
(観測実施対象)
注)・観測SA・PA:
名神、東名、中央の計19箇所のSA・PA。
・観測した自動水栓蛇口の種類:
メーカー、型式などの違いを考慮していません。
・SA・PA間のウエイト付:
SA・PAの利用頻度高低のウエイト付をしていません。
1.手洗い後、蛇口から手を引いた後も、水は必要以上にしばらくは流れ続ける問題
(1)SA・PAでの観測の結 果(手洗い後に余分に流れている
水の量)自動水栓で手を洗ってみると、洗い終わって手を引いても、水はさらにしばらくは余分に流れ続けていることが分かりました。そして、その余分に流れる量(流れ続ける時間)は、水流の強い蛇口ほど大きいことも分かりました。
1回手を洗うたびに、余分に流れる量(余剰流水量と呼ぶこととします)の最も小さかったSAで、0.02Lで、この19箇所の平均値は 最小値の約8倍に当る0.17Lとなっています。(下図)
また、最も大きかったSAで は、この余剰流水量は、1.0Lもあります。つまり1回手を洗った後に、余分にこれだけの水量が無駄に流れ出ている、と言うことになります。(下図)
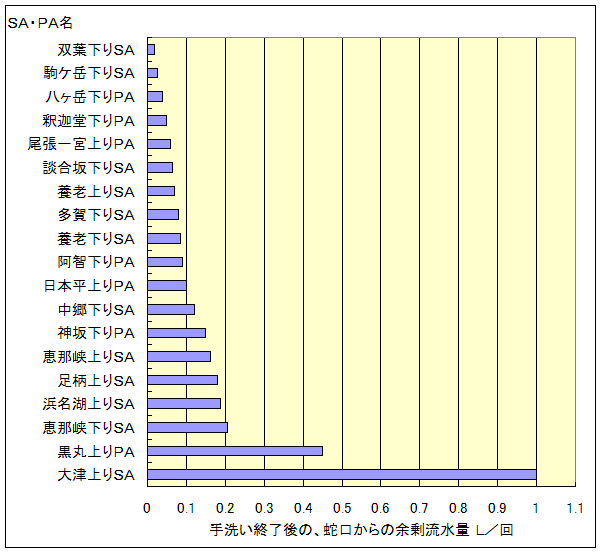
(2)手洗い後の余剰流水量に差が出る問題の原因
a.余分に流れている時間の長さの問題余分に 流れ続けている「時間」は、最短のSAで0.5秒間、最長のSAでは4秒間と長く、その差は3.5秒と、蛇口間で、大きくばらついています。 この流れ続ける時間は、 水流の強さ(吐水量と呼ぶこととします)の大きい方が長くなることが分かりました(下図)。
なお、一方、手洗いに支障の無い水流の最小限の強さは、2L/分程度、と言うことも確認できましたが、このとき余分に流れ続ける時間(量)を最も小さく出来、節水の面では好ましいと分かりました(例:双葉下りSA、駒ケ岳下りSA)。
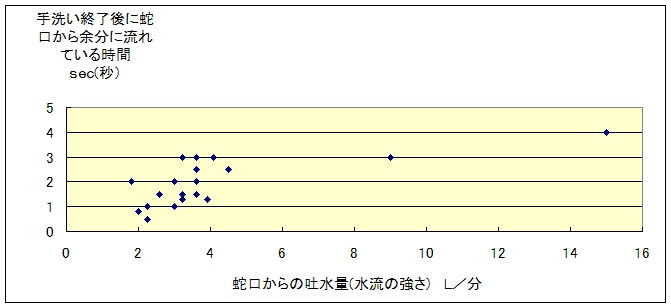
b.手洗い後の余分に流れ出る量の問題
この余分に流れ出る「余剰水の量」については、観測の結果、吐水量(水流の強さ)と比例関係にあることが分かりました。(下図)
この量についても、やはり、 吐水量を2L/分程度に小さく調節することが、余分に流れる量を小さく出来、節水の面では好ましいと分かります。
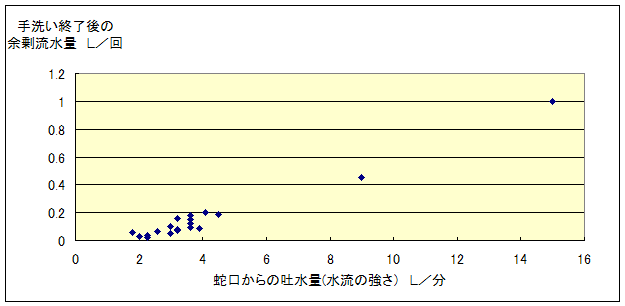
c.各SA・PAの余剰流水量と、蛇口からの吐水量(水流の強さ)の関係
この「蛇口からの吐水量」と、「余剰流水量」とを、各SA・PAごとに図の上で重ねてみますと、両者に関連のあることが分かります。(下図)
このことから、吐水量 を小さく適切に調節することが、余剰流水量を小さく抑える(水の無駄消費量を防止する)ことになる、と分かります。
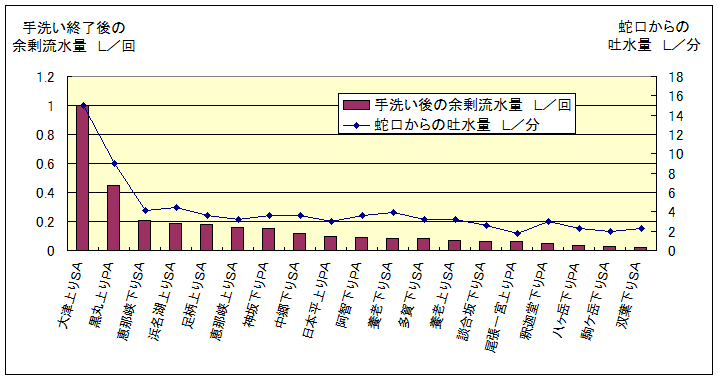
(3)手洗い後の余剰流水量の無駄消費量・・全国全てのSA・PAの平均的値
a.無駄消費量計算の方法ここで、余剰流水量の無駄消費量の算定方法について考えてみます。
余剰流水量の最も少ない「双葉下りSA」を、「省エネ SA・PA」として、観測19箇所の「SA・PAの全体平均値」との差を求めて、これを無駄消費量とすることにして考えてみます。
なお今後、この 「観測19箇所の『SA・PAの全体平均値』」を「全国全てのSA・PAの平均的値」とみなして考えることとします。b.手洗い後の余剰流水量の無駄消費量
手洗い後の余剰流水量は、 「全国全てのSA・PAの平均値」では、1回手を洗うたびに、「省エネSA・PA」に比べて約8倍に当たる0.15Lの水を余分に消費していると推定できます。(下表)
なお、「吐水量(水流の強さ)の最も大きかったSA」では、手洗い後の余剰流水量は、1回当たり、約1L にもなっています。
| 省エネSA・PA | 平均的SA・PA(全国の平均も同じとする) | ||
| (双葉下りSA) | 平均値 | 省エネSA・PAより余分に 消費する水量(無駄消費量) (平均SA・PA-基準SA・PA) |
|
| 蛇口からの吐水量(水流の強さ) (L/分) |
2.25 | 4.07 | ― |
|
手洗い終了後に流れている時間 |
0.5 | 2.0 | ― |
|
手洗い終了後の余剰水量 |
0.02 | 0.17 | 0.15 |
2.蛇口の水流が強すぎて、
手洗い中に水が無駄に消費されている問題
(1)SA・PAでの観測の結果(水流の強さ)
a.手洗い中の水無駄消費の問題
自動水栓で手を洗ってみますと、蛇口からの水流の強さがちょうど良く感じる所と、むやみに強すぎると感じる所など、今回観測した19箇所の各SA・PA間で、バラツキのが大き いことが分かりました(上図)。
吐水量(水流の強さ)の最も小さかったSAで約2L/分、最も大き
かったSAで約15L/分、とその差は、比率で7.5倍にもなります。
なお、この19箇所の平均値は、約4L/分 となりますが、これは最小値の2倍となっています。
b.水流の強さは、どの程度が良いか
吐水量(水流の強さ)の最も小さい「駒ケ岳下りSA(2L/分)」と、次いで小さい「双葉下りSA(2.3L/分)」で、手を洗ってみても全く問題がありません。
つまり、水流はそれほど強くしなくても、手洗いには支障の出ないことが分かりました。 蛇口からの吐水量(水流の強さ)は約2L/分で良いことになります。(最も水流の強い蛇口では、15L/分にもなっている)
(2)手洗い中の無駄消費量・・全国全てのSA・PAの平均的値
a.無駄消費量の計算方法この 手洗い中の無駄消費量の算定方法については、吐水量の小さい「双葉下りSA」を「基準SA・PA」として、観測19箇所の「SA・PAの全体平均値 」との差を求め、これを無駄消費量とすることにします。
なお今後、この「観測19箇所の『SA・PAの全体平均値』」平均値を「全国全てのSA・PAの平均的値」とみなして考えてみます。b.手洗い中の無駄消費量
この計算方法により、 「全国全てのSA・PAの平均値」では、1回手を洗うたびに、無駄消費量は「基準SA・PA」に比べて、 約1.8倍の0.1 5L/回となります。(手洗い時間の平均値を仮に5秒間として)無駄消費量は、1回の手洗い時間の長さと比例関係にあります(下表)。
なお、「吐水量(水流の強さ)の最も大きかったSA」では、手洗い中の無駄消費量は、1回当たり、約1L にもなっています。
|
1回の手洗い時間 sec(秒) → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 手を洗っているときの消費水量 (L/回) | 省エネSA・PAの場合 | 吐水量: 2.25L/分 |
0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| 全国平均的SA・PAの場合 | 吐水量: 4.07L/分 |
0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
|
全国平均的SA・PAが手洗い中に余分に消費する水量 |
省エネSA・PAとの差 |
|
0.03 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
0.15 |
0.18 |
3.損失水量の合計(手洗い後の余剰流水量の無駄消費量+
手洗い中の無駄消費量)
(1)1回の手洗いで損失する水量上記二つの無駄消費水量「手洗い後の余剰流水量の無駄消費量」「手洗い中の無駄消費量について、それぞれ全国SA・PAの平均的値な損失を合計してみます。
・手洗い時間が5秒としたとき、1回手を洗うたびに、無駄消費水量は、0.3L/回、すなわち、300cc、コップ約1杯半の損失となっていることが分かります(下表)。・ なお、なお、「吐水量(水流の強さ)の最も大きかったSA」の蛇口では、1回手を洗う度に、最大、約2Lの水を無駄に消費していることになります。(手洗い後の余剰流水量+手洗い中の無駄消費量)
| 手洗い中の水無駄消費量 | 手洗い後に流れ出る水の余剰流水量 | 手洗い1回当たりの水損失量合計 | |
| 1回の手洗い時間 sec(秒) |
水無駄消費量 L/回 ① |
余剰流水量 L/回 ② |
L/回 (①+②) |
| 1 | 0.03 | 0.15 | 0.18 |
| 2 | 0.06 | 0.21 | |
| 3 | 0.09 | 0.24 | |
| 4 | 0.12 | 0.27 | |
| 5 | 0.15 | 0.30 | |
| 6 | 0.18 | 0.33 | |
(2)全国のSA・PAで、年間に損失している水量と金額の合計
a.自動水栓手洗いの延べ利用者数(利用回数)の算定(推定値)全国のSA・PAでの水の年間の合計損失量を求めるために、 全国のSA・PAの自動水栓手洗いを利用する年間延べ人数(延べ回数)を算定する必要があります。
次の方法で、延べ約9億 9千万人/年、と算定することができます(下表)。
| 全国の高速道路 通行台数 |
全国高速道路1日の合計通行平均台数 | 台/日 | 4,041,687 | ① | 平成15年度の各インターチェンジの出交通量の合計(日本道路公団データ ) |
| 年間の通行台数 | 台/年 | 1,475,215,755 | ② | ①*365 | |
| 高速道路利用者数 | 1台の車に乗っている平均的人数 | 人/台 | 2 | ③ | 推定値 |
| 高速道路利用者人数 | 人/年 | 2,950,431,510 | ④ | ②*③ | |
| SA・PA利用者数 | 高速道路に1回入ってから出るまでに、SA・PAを利用する回数 | 回/回 | 1 | ⑤ | 推定値 |
| 年間のSA・PA利用人数 | 延べ人数/年 | 2,950,431,510 | ⑥ | ④*⑤ | |
| SA・PA利用者の内、トイレを利用する人数 | SA・PAを利用する人の内、トイレを利用する人数の割合 | 人/人 | 0.7 | ⑦ | 推定値 |
| トイレを利用する人数 | 延べ人数/年 | 2,065,302,057 | ⑧ | ⑥*⑦ | |
| 自動水栓設置比率 | 自動水栓と手動水栓の合計に対する自動水栓比率 | 台/台 | 0.8 | ⑨ | 推定値 |
| 自動水栓手洗いを利用する人数 | トレイ利用者の内、 手を洗う人の割合 |
人/人 | 0.6 | ⑩ | 推定値 |
| 自動水栓で手を洗う人の人数(回数) | 延べ人数/年 =延回数/年 |
991,344,987 |
⑪ |
⑧*⑨*⑩ |
b.全国のSA・PAの 、年間に損失する水量と金額
上記「手洗い1回当たりの水損失量合計」を基に、全国の年間の損失水量を求めてみます。
・損失水量・費用は、1回の手洗い時間の長さにより異なりますので、1秒~6秒の間で試算してみました(下表)。
・ 今仮にこの時間を5sec(秒)としますと、 年間の合計無駄消費水量は、約30万m3、損失費用は、年間約7千7百万円、と極めて大きな値とな ることが分かります(下表)。