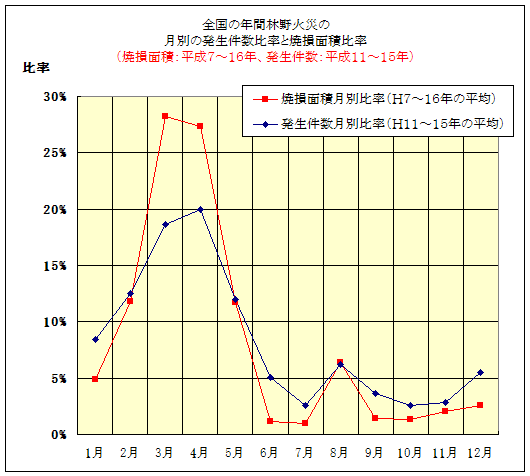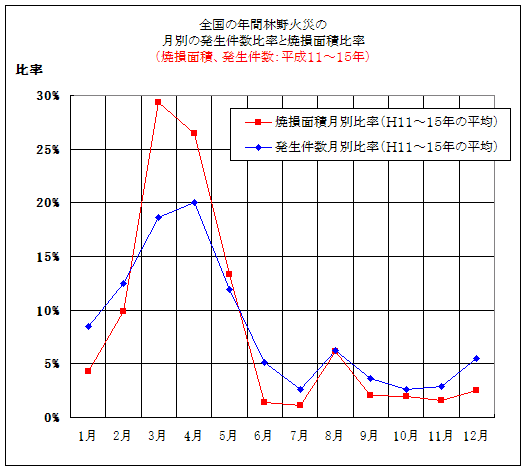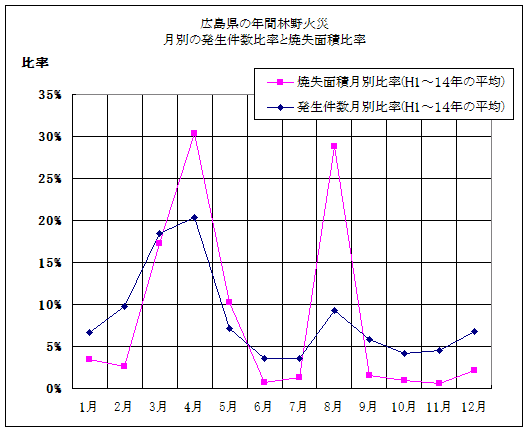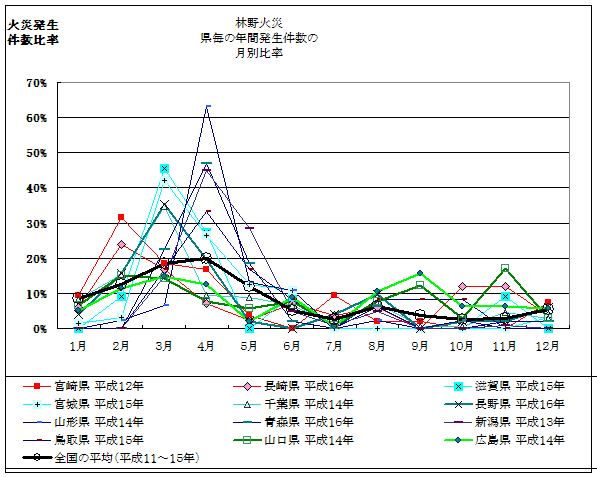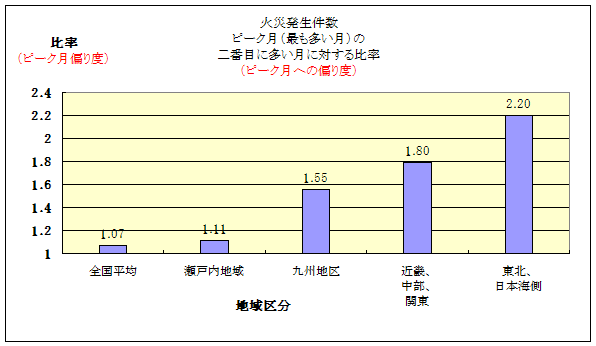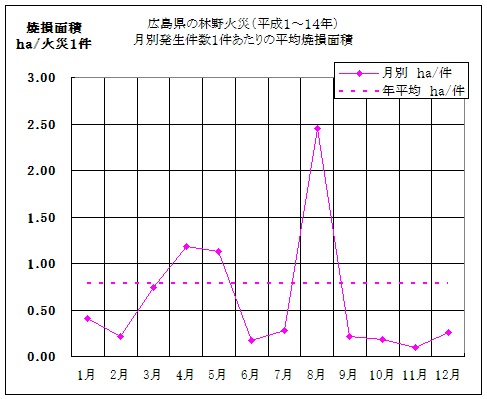(1)危険月では、「焼損面積」の比率は、「発生件数」比率を大きく上回る
全国の年間林野火災の「発生件数」と、「焼損面積」の各々の月別対年間比率を求めてみました。(図1)
(図1) 原データ出典:総務省消防庁 (その1)
① 危険月では、「焼損面積の年間比率」が、「発生件数比率」を大きく上回る全国のデータ(図1)で、林野火災は3月と4月がピークで、このとき 、各々の月において、「発生件数」が対年間比率が、約20%であるのに対して、「焼損面積」の方は同、約30%、と発生件数の比率を大きく上まわっています。
つまり、危険月においては、火災1件当りの焼損面積が、他の月より異常に大きい値を取ることが分かりました。
危険月では、いったん火災が発生すると、大きくなる、と言うことです。
つまり、火災の「発生件数」だけでは、「焼損面積」を予測出来ないことに気付くべきです。